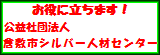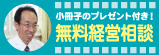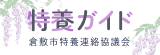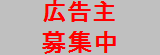こどもの貧困
倉敷市では約8,500人のこどもたちが
経済的に苦しい生活を送っている

日本の相対的貧困率は先進国の中でも高く、貧困状態にあるこどもたち(18歳未満)の人数では約9人に1人の状況です。つまり、1クラス(35人学級)では約4人のこどもが貧困状態にあるということになります。これを倉敷市の人口(令和6年3月)に当てはめると、約8,500人のこどもたちが、経済的に苦しい生活を送っているという計算になります。
満足に食事を取ることができない、経済的な理由で進学を諦める、必要な学用品をそろえることができない、親が昼夜問わず働いていて小学生のこどもが夜一人で過ごしているなど、生活困窮世帯には経済的な物が買えないだけではなく、栄養や教育、生活必需品、体験等が不足するなど、一般家庭では「当たり前に」あることが「ない」こどもがいます。
生活困窮世帯のこどもたちの状況の例
- 生活困窮世帯でクリスマスにサンタクロースがプレゼントを持ってきたことがない。
- 夏休みに夕食以外のご飯を食べることができず、休み明けには5kg痩せてしまった。
- 鍵盤ハーモニカ、習字道具、水着などの学用品が買えず、授業の時は毎回忘れたことにしていて、参加できない。
- 洗濯機が壊れて新しいものが買えないため、臭いがする汚れた服を着て学校に行っており、友達から避けられている。
- 高校進学をしたが、学校でかかる自己負担分の費用の支払いが難しくなり、退学せざるを得なくなった。
- 部活のユニホームが買えず、試合のときも体操服で参加し、恥ずかしい思いをしている。
ひとり親世帯の半数が貧困状態
日本のひとり親世帯の相対的貧困率は48.1%(※1)です。これは、ひとり親世帯の約半数が経済的に困難な状況にあることを示しています。O E C Dのデータによると、日本はひとり親世帯の就労率は先進国第1位にも関わらず、ひとり親世帯の貧困率が世界で最も高い水準(※2)になっています。
一方、デンマークでは、充実した福祉政策によりひとり親世帯の就労率が高く、貧困率が低い水準にあります。
日本のひとり親世帯は世界一働いているにも関わらず世界一貧困の状況の「世界一のワーキングプア」といえ、この状況は「自助努力の不足」や「自己責任」ではなく、社会構造の問題と考えられます。
(※1) 令和5年国民生活基礎調査(厚労省)
(※2) O E C D Family Database Table LMF1.3


7割の母子家庭は養育費を受け取れず、公的な支援も不足

個人の所得の総収入から税金や社会保険料などを控除した後、手当等の社会保障給付を受けることで、国民の経済格差を埋めるための仕組みである「所得の再配分」。日本は諸外国と比べて社会保障(手当等)や所得の再配分が小さいために、再配分後においても、収入が低い世帯が貧困の状態のままとなっています。特に現役世代の生活困窮世帯に対する再配分が小さいと言われています。現役世代への社会保障給付が少ない中で、昨今、少子化対策としても注目されている家族政策支出等も少ないことが、特にこどものいる世帯の相対的貧困率を高くしている原因となっている(※1)といわれています。
また、養育費を受け取ることのできている母子家庭が少ないことも、貧困に拍車をかけています。養育費を受け取っている母子世帯は28.1%(※2)に過ぎず、離婚後に養育費を受け取れていない母子世帯が7割と、世界と比べても受け取っている世帯が非常に少ない状況となっています。母子家庭の平均年収は272万円(※3)と一般世帯の552万円(※4)と比べて非常に低くなっていることに加え、養育費未払い問題があることで、経済的に厳しい母子家庭をさらに苦しめる要因の一つにもなっています。
さらに、男女の賃金格差も母子家庭の貧困に大きく影響しています。日本では、男女間賃金格差が世界の主要先進国と比べても、トップレベルで高い状況となっており、女性の平均賃金は男性の約75.2%(※5)にとどまっています。
(※1)令和3年所得再配分調査報告書(厚労省)
(※2)令和3年度全国ひとり親世帯等調査(厚労省)
(※3)最新/令和3年度全国ひとり親世帯調査
(※4)令和3年度国民生活基礎調査
(※5)男女間賃金格差(我が国の現状) | 内閣府男女共同参画局
こどもの将来に大きく影響する親の年収

親の収入とこどもの学力は密接に関連しています。世帯年収とこどもの学力を調べた研究では、世帯収入の高い家庭のこどもほど学力が高い傾向にあり、世帯年収の低い家庭のこどもほど学力が低い傾向があるという結果が出ています。また、両親の年収とこどもの高校卒業後の進路を調べた東京大学の調査では、世帯年収が低ければ低いほど大学進学率が低くなり、就職を選択するこどもは多くなっている一方、世帯年収が高ければ高いほど、大学進学するこどもは増え、就職を選択するこどもは少なくなっているという結果となっています。さらに、学歴と生涯賃金を比較したデータを見てみると、中卒の男性の生涯年収1億8890万円に対して、大卒の生涯年収は約2億6140万円であり、約8000万円もの収入の差があります。働く期間を40年間として捉えると年間200万円の格差があるという計算です。このように日本では、生まれた世帯によって学力が決まり、将来の進路や収入にまでも影響が出る状況にあると考えられ、このような状況が「貧困の連鎖」の一因になっているといわれています。

また、これらの教育の格差は、経済的貧困が原因になるだけではなく、親に病気や障がいがあるなどでこどもを支える力が不足している「機能不全家庭」や、親の代わりに親族の介護や小さな兄弟姉妹の世話をしたり、外国人世帯で日本語を話せない親のために学校を休んで通訳をしているなど、いわゆる「ヤングケアラー」の状況にある家庭のこどもにおいても同様に起こっています。
「人生を生き抜く力」が低くなる現実
こどもが健やかに成長していくためには、物事を覚えたり、考えたり、計算したりなど、IQや学力テストなど数値ではかれる力である「認知能力」と、忍耐力、意欲・向上心、回復力、自信・自尊感情、楽観性、コミュニケーション力など、「人生を生き抜く力」である「非認知能力」が必要になるといわれています。しかし、生活困窮世帯のこどもは、非認知能力が低くなる傾向にあるという調査報告があります。
非認知能力が高いと、どんなことにでも前向きに取り組み、人の意見を聞いて協力し合いながら挑戦し、失敗しても立ち直り、諦めずに再度挑戦できたりなど、まさに「生き抜く力」が高く、非認知能力が高いこどもであれば、生活困窮世帯に生まれたとしても大人になって自力で貧困から抜け出すことができるともいわれています。一方、非認知能力が低い場合は、自分の人生はどうでもいいなどパワーレスの状況になってしまったり、高校や大学に入学して問題にぶつかってしまうと中退してしまったり、社会人になっても仕事をすぐに辞めてしまい、最悪の場合は挫折から立ち直れず、人生まで諦めて「自殺」してしまうということもあります。
生活困窮世帯のこどもの非認知能力が低い原因としては、親が昼も夜も働いていたりでこどもと関わる時間の少なさ、栄養不足、体験格差などが指摘されていますが、小学校低学年の時点から非認知能力が低い傾向は見られるため、こどもが小さい段階からの対策が求められています。
貧困世帯※における学力の高いこどもと低いこどもの非認知能力偏差値

出典:公益財団法人 日本財団 家庭の経済格差と子どもの認知・非認知能力格差の関係分析 2.5万人のビッグデータから見えてきたもの(2018年1月)
貧困世帯における学力の高いこどもと低いこどもの非認知能力偏差値
生活困窮世帯のこどもたちが直面している問題
貧困層のこどもたちは、経済的困窮だけでなく、学習理解度や意欲、進学意欲、自己肯定感、生活習慣の定着など多くの面で困難に直面しています。彼らは不登校や低学力、将来の夢や進路に対する希望の欠如などの課題を抱えやすいといわれています。基本的な生活習慣が身についていないために不登校になることもあります。
また、職業モデルの偏りにより、将来の職業選択に制限を感じ、学校での努力の意義を見出せないことが多いです。
さらに、困難を抱えていても周囲に支援を求められず、社会的孤立に陥りやすいという問題もあります。
低所得世帯やひとり親世帯では、困ったときに頼れる相手が少ないため、こどもたちは多次元での困難に直面しています。
十分な食事を取れていない
- 栄養の偏った食事をしている
- 毎日朝ごはんを食べていない
- 一人やこどもだけでの食事
- 夏休みなどの長期休暇に食事が取れていない
- 赤ちゃんのミルクが買えない
家庭環境等によって本人の進学の選択肢が制限される
- 制服の購入ができない
- 学習の土台となる非認知能力が低い傾向がある
- 入学・通学に必要なお金が不足している
生活必需品が不足している
- メガネ、自転車等が購入できない
- 身体の成長や季節に合わせた服がない
基本的な生活習慣が身についていない
- 清潔な服を着ることができない
- 歯磨きの習慣が身についていない
- 朝学校に時間通りに通えていない
基本的な社会性が身についていない
- 親と一緒に過ごす時間が少ない
- 経済的・家庭の事情で部活に入れない または好きな部活を選べない
- ひとり親世帯や低所得世帯は文化的な体験(美術館・博物館・スポーツ観戦)ができない
こども時代に誰もが経験していることができない
- ひとり親世帯や低所得世帯は誕生日やクリスマスを祝う割合が低い
- ひとり親世帯や低所得世帯は家族旅行に行く割合が低い
事例
高校の入学式に制服を用意して参加できず、学校に行けなくなってしまう芽衣さん(仮名)

芽衣さんはこの春、定時制高校に合格しました。入学式を迎えるはずの芽衣さんの心は、期待と不安が入り混じっていました。
というのも、入学にかかる費用が足りず、制服を準備することができなかったのです。
高校に相談すると、「制服を買うお金がたまるまで中学校の制服で通学していい」と言われたため、芽衣さんは仕方なく中学の制服で入学式に臨みました。
入学式当日、新しい制服を着て輝いている同級生たちを見て、芽衣さんは恥ずかしさを感じました。そして、参列した保護者たちがこちらをチラチラ見てささやき合っている姿を見て、「またか・・・」と顔を上げることができませんでした。
明日からの学校生活でもそのような視線にさらされるのかと思うと憂鬱な気持ちが募り、次の日から学校に行けなくなってしまいました。
芽衣さんの母親は、学校に行けなくなった芽衣さんを心配していましたが、ひとり親で日々の生活費を稼ぐのが精一杯のため、経済的な余裕はありませんでした。担任の先生も心配し、制服の購入を支援してもらえる方法を探したところ、制服リユースの活動をしている地域ボランティア団体を見つけることができ、制服を提供してもらうことで、無事、学校に行けるようになりました。
新しい学校生活に出遅れてしまった芽衣さんでしたが、学校のサポートもあり少しずつ自信を取り戻すことができています。
すべてのこどもが「育つために当たり前にあるべき環境」が得られる社会を実現するために
一般のこどもたちの生活と比べ、生活困窮世帯や機能不全家庭では「こどもたちが育つために当たり前にあるべき環境が不足している」現状を踏まえ、本会では、「すべてのこどもが『育つために当たり前にあるべき環境』を得られる社会の実現」という目標を掲げて活動しています。
そして、最も大きな「不足」が集中している「食事」「進学」「生活必需品」「医療」「生活習慣」「社会性」「体験」「非認知能力」「世帯の生活力とこどもを支える力」の9つの視点に焦点を当て、社会問題に対する対処療法に留まらず、根本治療や予防となる活動も行い、貧困の連鎖を断ち切り、社会的インパクト(成果)に繋げることができる活動を行います。
「こどもの貧困」の解決に向けた取り組み
十分な食事が得られるための活動
こども食堂支援活動(設立支援・運営相談)、互近助パントリー普及&支援活動
本人の進学の自由をつくる活動
教育支援資金貸付事業、学用品等回収・配付活動
必要な生活必需品が得られるための活動
互近助パントリープロジェクト
適正な医療を受けることができる活動
健康保険再取得サポート活動、無料定額診療所紹介活動
基本的な生活習慣を身につける活動
基本的な社会性を身につける活動
こどもボランティア・マッチング活動
誰もがこども時代に体験していることができる活動
非認知能力(人生を豊かにする力)を高める活動
世帯の生活力やこどもを支える力を向上させる活動
技能習得費貸付事業、相談窓口
こどもが貧困であることは、格差の固定化、教育機会の喪失、虐待、犯罪、経済損失などあらゆる社会課題に根深く関わっていきます。
倉敷市を支えるためにあなたの支援が必要です