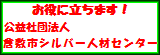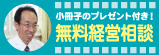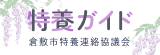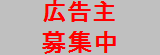移動困難問題
健康や生活水準を大きく低下させる「移動困難問題」

昨今、免許を返納して運転が出来なくなる人が増えるなか、「移動困難問題」が着目されています。
高齢者の交通事故が着目されるようになり、免許返納件数は令和元年の約60万人をピークに、減少傾向ではあるものの毎年数十万人が免許を返納するような状況が続いています。
一方、国の高齢者の生活環境を調べた調査(※)によると、困りごとの一番目が「日常の買い物に不便」、二番目が「医院や病院への通院に不便」、三番目が「交通機関が高齢者には使いにくい、または整備されていない」と、移動困難問題に関係するものが上位にあがっています。
「移動困難問題」は、単に買い物や通院などに困るような問題として捉えられていることが多いですが、食料や生活必需品を揃えることができなくなることから、お金があっても生活困窮のように栄養状態や生活の質を低下させる原因となり、さらに病気や障がいなどの必要な治療も困難な状況に陥る人もいるなど、深刻な問題となりうる問題です。
また、外出が減り、人に会う頻度も減ることから、孤独・孤立の状況に陥る原因になったり、運転をしなくなることで、認知症や要介護状態となる原因となることもあります。
(※)シニア層の住宅と生活環境に関する全国調査(内閣府「令和5年度高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」)
移動困難者に起こっていること
- スーパーまで徒歩30分以上かかってしまうため、夏場はお刺身、お肉、牛乳など、炎天下で傷みやすいものは買って食べることができていない。
- 免許返納後、好きな時に移動できなくなってから、1ヶ月に1度程度しか、人と会って話すことがなくなり、寂しい思いをしている。
- 治療が必要な病気があるが、かかりつけの病院に通うことが難しく、十分な治療ができなくなり、病状の悪化につながった。
- 徒歩での買い物のため、トイレットペーパーやティッシュペーパーなどの大きなものや、醤油、油、洗剤など、重いものも持って帰りづらく、いつも不足している。
- 年金が少ないことから、高齢でも働き続けているが、近年、事故を度々起こすようになり、免許返納を促されることが増えたが、公共交通機関では通勤が困難なため、免許返納ができない。
- 長年連れ添った妻の墓参りに行きたいが、お墓が車でないと行くことが難しいところにあるため、もう5年以上訪れることができておらず辛い。
移動困難者の推移

運転免許統計より
警察庁交通局運転免許課令和5年版

倉敷市地域公共交通計画(令和6年2月変更)より
移動困難によって起こる社会問題
運転を中止した高齢者は、運転を継続していた高齢者と比較して、要介護状態になる危険性が約8倍上昇すると報告されていますが、移動困難の課題は、単純に移動ができなくなるだけでなく、生活水準や健康寿命を低下させ、孤独・孤立問題も悪化させ、人生の満足度まで低下せる大きな問題です。
例えば、生活において、買い物に行くことが困難になってくると、お刺身、お肉、牛乳など傷みやすいものは買えない、トイレットペーパーやティッシュペーパーなどの大きなものや、醤油、油、洗剤など、重いものも買えないということも発生し、定期的に買い物ができなくなると、お金があっても生活必需品が不足しているという、生活困窮者と変わらない生活になることもあります。
また、通院が困難になることも、問題です。透析や高血圧、糖尿病の治療、時には癌など、定期的に受診し、治療を行わなければならない病気もありますが、移動困難により、通院できず、病状が悪化されるケースもあります。
加えて、孤独・孤立問題を悪化させてしまうのも重大な問題です。孤独孤立は、睡眠不足の次に体に悪影響があるものと言われており、肥満、運動不足、タバコ、飲酒などよりも悪く、生活習慣病を増やして健康寿命を大きく下げ、介護になる可能性を上げるものになりますが、その状況を間接的に作り上げてしまう社会問題が「移動困難」でもあります。
この移動困難問題は、余暇活動等の社会参加のための外出を困難になるだけではなく、金融機関での手続きや日用品の買物、通院など社会生活上必要不可欠な移動を困難にし、健康寿命の悪化、孤独・孤立化、買い物難民による生活の質の低下、医療や福祉サービスへのアクセスの低下など、多くの生活問題が発生するようになります。
こうした社会問題は、それぞれが関連し、移動困難者にとっては、重大な生活課題となっています。
生活の質の低下
移動が困難なため、食べたいものが食べられない、着たい服を着ることができないなど、人の基本的な欲求を満たすことができなくなると健康を害したり、生活水準の低下につながります。さらに、お金があっても日常生活に欠かせないものが必要な時に買えない。このようなことが起こり、移動困難が要因により買い物難民となり、生活困窮状態に陥ることも考えられます。
また、高齢者を中心に本人に出かける意欲があっても、そこまで行けないという問題は深刻で、特に通院が困難になることは生命に関わる大きな問題です。在宅医療で対応できる場合やオンライン診察等で対応できるケースは良いですが、どれだけの医師が在宅医療に従事しているかを考えると、やはり移動困難者は医療難民化する深刻な課題といえます。
健康寿命の低下
高齢者における移動問題は、高齢になってもマイカー運転を続けて交通事故を起こすリスクと、マイカー以外の移動手段が確保されていないために、運転できなければ外出困難になるリスクの両方の側面があります。
高齢者がひとたび運転をやめると、急に外出が減ります。国土交通省の調査(※)によると免許がない高齢者は、免許がある人に比べて外出率が低くくなっています。
また、運転を中止した高齢者は、運転を継続していた高齢者と比較して、要介護状態になるリスクが約8倍上昇すると報告されています。
※「第6回全国都市交通特性調査(2015年)」
孤独・孤立
内閣官房孤独・孤立対策担当室の「人々のつながりに関する基礎調査(令和5年)」によると、孤独感が「しばしばある・常にある」、「時々ある」又は「たまにある」と回答した人で、現在の孤独感に影響を与えたと思う出来事について聞いた結果では、1位「家族との死別」で23.3%、次いで「一人暮らし」19.5%、3位が「心身の重大なトラブル(病気・怪我等)」15.5%となっており、人との関わりがなくなったり少なくなった際に孤独感が生まれやすいことが分かります。
また、たとえ外出や人と関わりたいという欲求や意欲があったとしても、そのための移動手段が確保されないことにより、その欲求や意欲は阻害されてしまいます。移動困難者は移動が困難なことから外出が減り、人と会う機会自体が移動できる人より減少することで、孤独・孤立となるリスクも増えています。

令和5年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果より
内閣府

「食品アクセス問題」に関する全国市町村アンケート調査結果より
林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課令和6年3月
事例
70代後半の男性Aさんは、大手企業の重役まで勤め、子ども3人を大学卒業まで育てました。子どもが独立したことから、退職後は夫婦二人で悠々自適に暮らすことを考えていました。とても仲の良い夫婦で、よく夫婦二人で買い物に行ったり、近所の馴染みの店で食事をするなど、近所でも評判のおしどり夫婦でした。
しかし、数年前に奥さんが病気により体調を崩したことをきっかけに、施設入所することとなったことから、一人暮らしとなりました。しばらくは、買い物等身の回りのことは自身でされていたので、家族やご近所の方も安心していました。
また、車を運転して、会社勤めをしていたころからの趣味であった囲碁を指すために毎日囲碁サロンに出かけたり、奥さんが入所する施設に見舞いに行ったりして生活していました。
しかし、奥さんと通った馴染みの店での食事も一人、とても仲の良かった奥さんが自宅にいなくなった寂しさや、家での会話がなくなったことから、Aさん自身も次第に変化が表れていきます。
とても元気だったAさんですが、軽度ではあるものの車の事故を何度か繰り返すようになります。
Aさんが住んでいる地域は、公共交通機関がなく、車での移動が必要な地域ですが、事故を繰り返したことにより、ご自身も外出への不安を感じ頻度が減っていきます。
さらに、この頃、高齢者ドライバーの事故の増加に関する報道が増え、全国的に高齢者の免許返納が話題になったこともあり、家族からも免許の返納を勧められるようになりました。次第に、認知機能の低下も見られるようになり、何度か家族での話し合いを重ね、車の維持費のことを考えるとタクシーで移動した方が安全で良いのではということとなり、免許を返納することとなりました。
免許返納後、徒歩で行ける場所にスーパーがあったこともあり、徒歩で買い物に出かけることも可能でしたが、不景気のためそのスーパーが閉店してしまい、買い物は4.5km離れたコンビニや別のスーパーへタクシーで行くこととなりました。
一人暮らしのため、一度に買うものは、朝食用のパンと弁当と晩酌用のお酒で合計1,000円少々。この買い物のためには往復タクシー代が必要と考えるとAさんはもったいないという考えになります。
また、車を運転しなくなったことから、毎日通っていた囲碁サロンにも行かなくなり、奥さんとの思い出の場所である馴染みの店での食事をすることもなくなっていきました。次第に、毎日家でテレビを見るだけの生活となり、意欲の低下が顕著となり、認知症状も進行していきました。
ハンディによってひとりで移動困難な人が
日常生活に必要な外出ができる社会を実現するために
高齢や障がい、過疎等の地域特性などのハンディにより、移動困難者が多数いることを踏まえ、私たちは、「ハンディによってひとりで移動困難な人が、日常生活に必要な外出ができる社会の実現」という目標を掲げ、活動しています。
そして、日常生活における徒歩による移動、公共交通機関による移動、車に乗せてもらっての移動などに加え、日常生活以外の生活に必要な外出、店舗・建物内の移動等の問題に焦点を当て、社会問題に対する対処療法に留まらず、根本治療や予防となる活動も行い、社会的インパクト(成果)につなげます。
「移動困難問題」の解決に向けた取り組み
ハンディがあっても歩いて移動することができる
介護予防活動、ボランティアマッチング活動、いきいきポイント、サロン活動支援、福祉機器貸出事業、リサイクル事業、ガイドヘルパー養成、ガイドヘルプ体験講座(出前福祉講座)、高齢者・障がい者のための用水路等転落事故防止対策アドボカシー(代弁)活動
ハンディがあっても公共交通機関を利用しやすくなる
ガイドヘルプ体験講座(出前福祉講座)、障がい者等の事故防止に関するアドボカシー(代弁)支援活動
ハンディがあっても移動したい時に車等で移動できる
福祉車両貸出事業
ハンディがあっても決まった目的のための移動が無理なくできる
住民主体の活動支援
ハンディがあっても外出先の店舗・建物・敷地内に入り、目的の場所に移動することができる
補助犬受け入れに関するアドボカシー(代弁)支援活動、障がい者対応店舗増加を求めるアドボカシー(代弁)活動
ハンディのある人が困っているときに気にかけて声をかけてくれる人の増加
社会問題情報発信活動、寄付文化醸成活動
移動に関する社会問題の重要性を理解できている人の増加
移動に関する社会問題情報発信活動