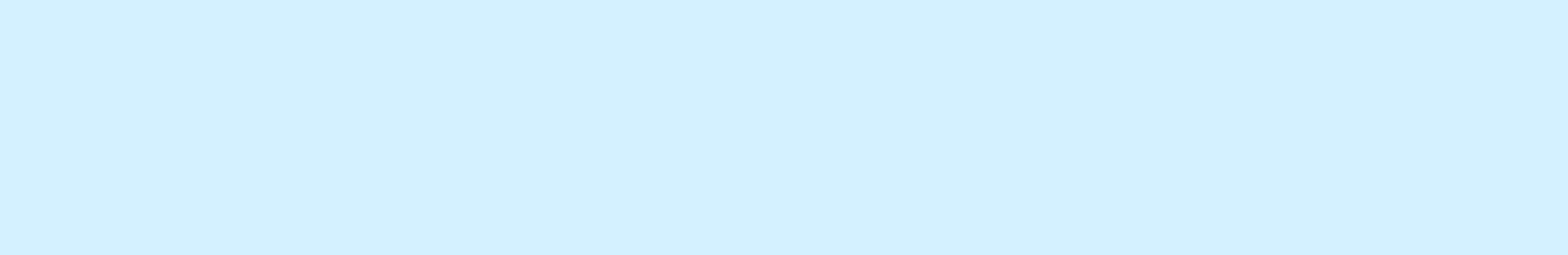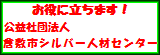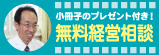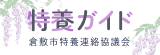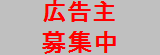権利擁護に関すること
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは?
 介護保険制度および支援費制度の導入により、福祉サービスの利用の仕組みは、自分で必要なサービスを選び、自らが契約を結んで利用する仕組みになりました。
介護保険制度および支援費制度の導入により、福祉サービスの利用の仕組みは、自分で必要なサービスを選び、自らが契約を結んで利用する仕組みになりました。
しかし、自分の判断能力に不安がある方は、どのような福祉サービスがあるのか、どのようにすればサービスを利用できるのかなど、様々な場面で判断に迷い、適切に福祉サービスを受けられない場合があります。
また、毎日のくらしに必要なお金の出し入れに困ったり、訪問販売による過剰な物品の購入などのトラブルに巻き込まれる場合も想定されます。
そのような方々が安心して生活が送れるようにお手伝いする事業がはじまっています。
この事業を「日常生活自立支援事業」といいます。
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者や障がい者の方々が、地域で安心して生活が送れるように、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや日常生活に必要な金銭管理のお手伝いなどをします。
どのような人が利用できるの?
在宅で生活されており、ご自分の判断で福祉サービスの利用や日常的な金銭管理について適切に行うことが困難な方です。
例えば、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などでつぎのようなことでお困りの方です。





社会福祉協議会がお手伝いします。
どのようなお手伝いをしてくれるの?
福祉サービスの利用援助
福祉サービスが安心して利用できるようにお手伝いします。
|
 |
日常的金銭管理サービス
毎日の生活に必要なお金の出し入れをお手伝いします。
|
 |
書類等の預かりサービス
大切な書類や印鑑などを安全な場所でお預かりします。
|
 |
お手伝いを利用するまでの流れ
1.相談お近くの社会福祉協議会にご相談ください。秘密は必ず守ります。 |
専門員が対応します 無料 |
|
2.訪問専門員がご自宅を訪問して、お困りごとなどをお伺いします。 |
||
3.支援計画・契約書の作成ご本人の希望をたしかめて、支援計画・契約書を作成します。 |
||
4.契約ご本人と社会福祉協議会とで契約を結びます。 |
||
|
|
||
5.援助の開始生活支援員が支援計画(契約書)にもとづいてお手伝いをします。 |
|
生活支援員が対応します 有料 |
どれくらいの利用料がかかるの?
| 福祉サービスの利用援助 金銭管理サービス |
書類等の預かりサービス | |
|---|---|---|
| 生活保護受給者 | 無料 | 利用料400円/月 手数料200円/年間 |
| 上記を除く者 | 1,100円/1時間 | 利用料400円/月 手数料200円/年間 |
- 福祉サービスの利用援助・金銭管理サービス利用料は、1時間を超える場合30分ごとに半額を加算した額とします。
- 生活支援員がお手伝いするときにかかる交通費は実費をご負担いただきます。
安心して利用していただくために
適正な事業運営の確保に努めるために、2つの会を設けています。
- 運営適正化委員会
事業運営の監視や利用者からの苦情を受け付けます。 - 契約締結審査会
契約を結ぶ上での理解のたしかさや支援計画の内容の適正さを審査します。
| お問い合わせ |
|---|
|
倉敷市社会福祉協議会 日常経済生活サポートセンター |
| この事業についての苦情 |
|---|
| 受付電話:086-226-9400 |
法人後見事業
認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を守るために家庭裁判所が後見人等を選ぶことで、本人を支援する制度が「成年後見制度」です。
法人後見事業では、本会が成年後見人等を受任し、財産管理や身上監護を行い、その人の権利を守ります。(任意後見人、未成年後見人は受任していません)。
法人後見運営委員会
本会が法人後見事業を行うにあたり、業務の公正性と専門性を確保するため、学識経験者、法律関係者、医療関係者、福祉関係者、行政関係者等で組織する法人後見運営委員会を設置しています。
法人後見運営委員会では、本会が成年後見人等を受任するかの適否の判断や、支援に対する専門的な助言を受けることにより、本人の意思を尊重した支援を提供します。
対象となる人
- 市長申立てをする者で、他に適切な後見人等が得られない人
- 原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない人
- 日常生活自立支援事業の利用者で、判断能力が低下した者のうち、第1号か第2号に当てはまる人
- 本会及び運営委員会が特に必要と認める人
※運営委員会で受任の審査を行い、必要と認めた場合に受任する。
利用料
1年毎に家庭裁判所に報酬付与の申立を行い、決定した金額を徴収します。