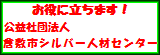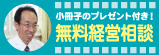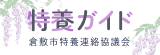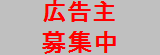災害問題
災害時に逃げ遅れる人がいる
早期に生活再建できない被災者がいる
|
あの災害を忘れない 平成30年7月5日から7日にかけて、梅雨前線の活動が活発化し、複数の線状降水帯が発生したことにより、災害が少ないと言われていた岡山県において、初めてとなる特別警報が発表されるなど、記録的な大雨が発生しました。 倉敷市真備地区では、地区内を流れる4河川の8カ所で堤防が決壊し、住宅街のほとんどが水に飲み込まれました。深さは最大5メートルにも及び、真備地区内の65%の家屋に被害が発生し、70名を超える方(災害関連死を含む)が亡くなるなど、岡山県では過去最大の被害となりました。 現在、河川の改修やまちの復興は次々と進んでおり、災害が起きたことを感じさせる機会はどんどん減ってきています。しかし、地球温暖化によって風水害が頻発化・激甚化しており、毎年日本各地で風水害や土砂災害が発生しています。また、南海トラフ地震等の発生も懸念されており、私たちはいつ起きるかわからない次の災害に備えておく必要があります。 災害発生をゼロにすることはできませんが、災害による被害を少なくすることはできます。あの災害を忘れることなく、次の災害に向けた取り組みを進めることが、被災経験のある社協に託された使命だと考えています。 |
人的被害の状況令和2年9月1日現在
住家被害の状況平成31年4月5日現在
|
岡山県内で5年に1度は災害が発生していた

岡山県は地震が少ない地域と言われていますが、過去の台風や集中豪雨などの記録を辿ってみると5年に1度は災害が発生しています。
また、政府の地震調査委員会によると、南海トラフ沿いでマグニチュード8~9級の巨大地震が、20年以内に起こる確率は60%程度、30年では70~80%、40年であれば90%程度になると発表されており、岡山県内にも多くの被害が出ることが想定されています。
このように、あなたの身近な地域でいつ災害が起きても不思議ではないことがわかります。
倉敷市内では、災害によってどのような被害が発生するのか考えてみましょう。市内を1級河川の高梁川と小田川が流れているため、台風や大雨によって河川の氾濫が懸念されます。また、瀬戸内海に面している地域では、台風による高潮被害や地震後に発生する津波の被害も想定されます。また、地震の場合には液状化現象によって地面からの噴水や地盤沈下などが起こり、多くの住家やライフラインに被害が及ぶことが想定されています。
岡山県内で災害救助法が適用された災害
| 災害発生年月日 | 災害種類 | 被害状況 |
|---|---|---|
| S51.9.13 | 台風17号 | 岡山県下3市11町で災害発生。死者17名、住家33,432戸に被害発生 |
| S52.9.3 | 集中豪雨 | 津山市で災害発生。住家2,680戸に被害発生 |
| S54.10.19 | 台風20号 | 柵原町で災害発生。死者3名、住家2,048戸に被害発生 |
| S56.7.13 | 集中豪雨 | 湯原町で災害発生。死者2名、住家534戸に被害発生 |
| H2.9.19 | 台風19号 | 岡山県下1市4町で災害発生。死者10名、住家8,080戸に被害発生 |
| H10.10.18 | 台風10号 | 岡山県下1市3町で災害発生。死者5名、住家7,396戸に被害発生 |
| H16.8.30 | 台風16号 | 倉敷市も含め、岡山県下5市4町で災害発生。死者1名、住家10,886戸に被害発生 |
| H21.8.9 | 台風9号 | 美作市で災害発生。死者1名、住家643戸に被害発生 |
| H23.9.2 | 台風12号 | 玉野市で災害発生。住家631戸に被害発生 |
| H30.7.5 | 集中豪雨 | 倉敷市を含め、岡山県下14市6町1村で災害発生。死者73名(災害関連死含)、住家15,294戸に被害発生 |
発災時に支援を必要とする人がいます
災害が発生すると、避難時や避難所での生活において配慮を必要とする人たちがいます。「要配慮者」と言います。この要配慮者が最も被災の影響を受けやすい人たちです。

これまでの災害で「要配慮者」に起こった課題
これまでの災害で「要配慮者」には、身体の状態や障がい特性によって、次のような課題が起こってきました。
東日本大震災では、災害によって亡くなった方のうち60歳以上の死者数が約6割であり、また、障がい者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍になっています。
平成30年7月豪雨災害の倉敷市でも、亡くなった方の約8割が70歳以上の方で、その多くが自宅の1階で亡くなっていました。災害情報が十分届かなかった、避難するタイミングを逃してしまった、身体が不自由で自分一人で避難ができなかったなどの原因が考えられます。高齢者や障がい者は、自らの力だけで避難することが困難な場合があり、地域で避難を進める取り組みが求められます。
被災者の支援のための社会福祉協議会の役割
倉敷市では、大きな災害が発生すると、倉敷市役所との災害協定に基づいて社会福祉協議会が「災害ボランティアセンター」を設置し、全国各地から集まるボランティアを受け入れながら、被災者が早期に日常生活を取り戻せるように支援を行います。
平成30年7月豪雨災害のときにも、社会福祉協議会では発災から4日後には「災害ボランティアセンター」を立ち上げ、多くのボランティアと被災者をつなぐ役割を果たしてきました。
被災者からは、「ボランティアが来てくれたおかげで助かった」「ボランティアに何度も励まされた」「ボランティアのためにもがんばらんとね」という声が、社会福祉協議会にはたくさん寄せられました。ボランティアは家の片づけや災害廃棄物を捨てるお手伝いをするという役割だけでなく、被災者の気持ちを支える、被災者の気持ちを前向きにさせる力を持っている大切な存在だということをあの災害を通じて学びました。「人を支えられるのは人だけだ」という思いを大切にし、被災者の生活再建のために、ボランティアの力とやさしさを丁寧につないでいくことが社会福祉協議会の役割だと考えています。


平成30年7月豪雨災害での倉敷市災害ボランティアセンターの活動実績

災害時の逃げ遅れゼロと被災者の早期の生活再建を実現するために
近年、災害が頻発化・激甚化しており、私たちの地域でもいつ災害が起こるかわかりません。ひとたび災害が起きると、高齢者や障がい者などの要配慮者に大きな被害を受ける可能性が高くなります。
そこで、私たちは『災害時の逃げ遅れゼロと被災者の早期の生活再建の実現』という目標を掲げ、計画(ロジックモデル)を作成しました。
具体的には、災害が発生する前や発生後の避難に関する取り組みを行っていきます。また、被災した自宅を少しでも早く片付け、元の生活に戻れるように、行政やボランティア、専門知識や技術を持ったボランティア団体などと連携して、早期の生活再建に取り組んでいきます。
課題解決に向けた取り組み
発災後の避難に関する課題
平時から避難持出物を準備している人を増やす活動
平時から避難持出物を準備しておくことの必要性を、社協だよりやホームページを通じて啓発していく
個別避難計画を作成している人を増やす活動
自ら避難行動ができない人(避難行動要支援者)に対して、個別避難計画を作成することを促進する
地区社協等による防災活動の支援
地域において避難に関する共通認識が図れるように、避難訓練や防災マップづくり等を支援する
被災者の生活再建に関する課題
災害ボランティアセンターの設置・運営
早期の生活再建ができるように、被災家屋の片付けや清掃活動などをボランティアに協力してもらうように紹介・調整を行う
被災世帯を戸別訪問する見守り・相談支援活動の実施
戸別訪問する中で、困りごとを相談機関につないだり、繰り返し訪問することで孤立の防止を図る
日用品・生活必需品等を配布する活動
日用品や生活必需品が不足する世帯に対し、支援物資が提供できるようにNPOやボランティア団体等との連携を図る
情報が届きにくい避難先にいる被災者への被災者支援情報の発信活動
情報を収集したり理解したりすることが苦手な被災者に対し、支援者が訪問し、情報提供や手続きの支援を行う