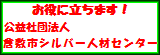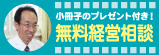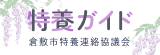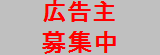親亡き後問題
障がいのある子どもがいる親の86%は
「親亡き後」に不安を抱えている
知的障がい者の家族向けの調査によると、「一緒に生活する家族などの高齢化や親なきあとの生活」に対して、86.0%の家族が不安を感じており、精神障がい、障がい児、発達障がいの家族への調査結果においても、同様に大きな不安を抱えている結果となっています。
年金の手続き、障害者手帳の更新などの公的な手続き、金銭管理、買い物、掃除、調理、洗濯などの身の回りの世話は親が担っていることが多く、亡くなった後の対応が社会問題となっています。
一人暮らしをする障がい者の中には、悪徳商法の被害に遭っても気づかず、何度も繰り返し被害を受けたり、税金などの支払い方法がわからずに延滞税が発生し、財産が差し押さえられたり、親切にしてくれる知人からお金を搾取される、地震などの災害時に避難の判断ができないなど、生活において問題が生じることが少なくありません。しかし、障がい者の親等はこのような心配がありながらも、子どもの面倒を最後まで見ることができないことから、いわゆる「親亡き後」を心配する親が非常に多くなっています。

親亡き後の障がい者に起きていること
親亡き後に考えられる生活上の主な問題
障がい者の生活において、家族が本人のことをよく理解し、身の回りのことや生活に必要な契約・手続きなどを多く手助けしています。
しかし、親が亡くなった後には、本人を理解し、身の回りの手伝いをしてくれる人がいなくなり、本人にとって当たり前だった生活ができなくなります。
また、社会とのつながりが薄れ、孤独や孤立の状態に陥ることも多くあります。
時には、悪質な業者や個人に狙われやすく、悪徳商法や財産侵害に遭うこともあります。
新たに住宅や施設に移る際に、保証人や緊急連絡先を見つけられないと、入居や入所ができない場合もあります。
さらに、災害時には情報が行き届かず、自身で判断ができない、あるいは自分だけでは避難行動が取れない場合もあります。実際に、災害時の障がい者の死亡率は一般よりも6倍高い状況です。

親亡き後に起こる主な問題
本人を親のように理解して支援する人がいない

一緒に暮らす家族は、本人のことをよく知っています。好きな食べ物や好みの服、よく行くお店、好きな場所、よく見るテレビ番組、趣味、生活習慣、決まりごとなどのこだわり、さらには嫌いなことや苦手なこと、受け入れやすいコミュニケーションの取り方についても理解しています。どんな時に怒るのか、どんな時に喜ぶのか、誰と話すのが好きで、苦手なタイプの人はどんな人かも把握しています。
障がいのある方にとって、このような決まった生活習慣は、精神的に安定して過ごすために非常に重要です。
例えば、着替え方には右手から手を入れるといった「こだわり」があることもあります。洗濯物を干す手伝いをしている際も、いつもと同じものを同じ順番で干していると問題はありませんが、途中で違うものを干すよう頼まれると混乱して作業ができなくなることもあります。また、嫌なことを「嫌」と言えない、したくないことを「自分でしたくない」と言えない場合には無言になってしまうこともあります。
このような「こだわり」や性格、趣味嗜好を理解している家族は、本人が何を望み、どうしたいかを察して対応できるため、事前にトラブルを避けることができます。これにより、本人が笑顔で楽しく過ごせるように、嫌な思いをしないように自然に配慮しながら生活を支えています。しかし、親が亡くなった後は、その「当たり前」を叶えてくれる人がいなくなってしまいます。
在宅生活の場合に身の回りの世話をしてくれる人がいない
家族と一緒に暮らしているときは、家族が食事の準備をし、家族と一緒に食べ、時には食事の手伝いをし、食後は食器などを片付けています。
また、家族が洗濯や掃除も行い、買い物や通院が必要なときは着替えも手伝い、車で連れて行きます。
そして、家に帰ったら、お風呂や歯磨きなども手伝い、寝る準備をして就寝します。
また、近所付き合いは、家族がいるときは家族が行っています。
しかし、親亡き後は、家族からのサポートが受けられなくなり、一人でお金のやりくりをし、買い物に行き、食事を準備し、食後の片付けをする必要もあります。
また、家の片付けや修繕、修理についても自力での対応が必要となり、洗濯や身支度も一人で行わなくてはいけなくなります。
近所付き合いも直接のつながりはないことが多く、親亡き後は近所で困った時に助けてくれる人は、なかなかいません。

厚生労働省HP 令和4年生活のしづらさなどに関する調査
(全国在宅障害児・者等実態調査)結果一覧 表45-55を参考に倉敷市社協で作成
生活に必要な契約・手続きが難しい

障がいの有無に限らず、生活には契約行為や手続きが必要です。例えば、携帯電話やインターネットの利用、保険の加入、引っ越し、アパートへの入居、障がい者施設や障がい福祉サービスを利用する際にも、契約行為や手続きが伴います。仕事に就く際には、雇用契約が必要です。通勤のために車やバイクなどを使う場合、購入契約を結ぶ必要があります。
さらに、給料を受け取るために銀行口座を開設し、そのお金で生活するためには引き落とし手続きが必要です。ATMの利用やクレジットカードの利用にも手続きが伴います。その他、住宅の修繕には業者との契約が必要で、契約に基づき支払いも行わなければなりません。病気になった場合は病院に入院しますが、入院手続きや医療を受ける範囲の判断についても考えなければなりません。自力で生活することが難しくなれば、施設への入所が必要となりますが、その際にも契約行為や手続きが求められます。
加えて、親族に関係した相続や財産処分が発生した場合、事故に遭ったときの保険金受給、社会情勢によって支給される給付金、受け取っていない障害年金など、手続きをしなければ受け取れないお金もあります。
実際、近年には年金生活者支援給付金(2019年より)、コロナ給付金(2021年)、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(2022年)、低所得者等支援給付金・定額現在補足給付金(調整給付)(2023年)などが給付されましたが、手続きをしなければ受給できませんでした。また、災害に遭った場合、罹災証明の申請をしなければ、公的な支援を受けることもできません。
金銭的・暴力的・性的被害に遭いやすい
障がいのある方の中には、社会経験が浅く、他人への警戒心が薄かったり、相手の頼みを断るのが苦手だったりするため、悪質な行為をする人に狙われやすい傾向があります。高額な健康食品の購入や架空請求などの悪徳商法、身体的な暴力や性的虐待など、さまざまな被害に遭うケースもあります。障がいのある方を狙って近寄ってくる悪意のある人も多い一方で、残念ながら本人が被害に気づかず、周囲に相談できないケースも少なくありません。そのため、被害が大きくなってしまうことがしばしばあります。
金銭的・暴力的・性的被害に遭った例
-
[事例1]
訪問販売できた人に、勧められて必要のない高額な栄養ドリンクを大量に契約。
-
[事例2]
知的障がいの女性に対して、親切を装って近づいてきた男性が、住まいに入り浸るようになり、暴力や暴言でコントロールし、障害年金の搾取および性的搾取を繰り返した。
-
[事例3]
「個人情報が洩れている」と携帯に詐欺電話がかかり、情報漏れを防ぐために振り込みを依頼され、指定口座に振り込みをしてしまった。
-
[事例4]
親が亡くなったのちの相続において、兄弟が理不尽に不平等な相続財産分与を決めてしまい、お金はもらえず、住んでいた家からは追い出されてしまった。
-
[事例5]
「ネットカジノで儲けようとした」というニュースを見て、自分もできると思い、スマホでネットカジノをしたが、お金は増えることはなく、 自己破産するまで、のめり込んでしまった。
災害時に被災しやすい

災害時には、要介護者や障がい者が被災しやすい傾向があります。過去の災害では、高齢者の次に障がい者の方が多く被災している現状があります。東日本大震災で被災した自治体の調査によると、障がい者の死亡率は、住民全体の死亡率の約2倍になっているという報告もあります。
実際、倉敷で発生した豪雨災害においても、倉敷市の死者(災害関連死を除く)52人のうち、高齢者を中心とした要介護・要支援者が19人(36.5%)であり、それに次いで、身体障がい者が12人(23.1%)と、占める割合が高くなっています。
また災害時、避難できたとしても、避難所での生活は障がいのある方にとって大きな負担となります。障がい特性に合った環境が整っているわけではなく、精神的なストレスや身体的な不自由を感じ、自宅に戻りたいと考える人も少なくありません。災害時には自宅で生活を続けることが困難なことも多いため、これは大きな課題の一つとなっています。
住む場所が確保できない

親亡き後、障がいのある方が賃貸契約の主体となると、家賃債務保証会社の審査に通らなかったり、保証人や緊急連絡先が確保できなかったり、収入状況などから家族と住んでいた賃貸物件の契約を更新できないケースも少なくありません。また、同様に新たな賃貸物件を探すことも容易ではありません。
さらに、精神的な疾患を抱えている人やコミュニケーションに困難を抱えている人は、入所施設を探す際にも難しいことが多くあります。法律上、保証人がいなくても入所を妨げる理由にはなりませんが、実際には多くの施設が保証人や緊急連絡先を求めており、入所が困難になるケースがあります。特に、トラブルが多くなる傾向がある人や、他者と関係を築くのが難しい人の場合、受け入れてもらえる施設が見つからないという事態に陥ることがあります。
倉敷市にある親亡き後の事例
私は夫と子どもと3人で暮らしていました。夫は会社員として働き、私はスーパーでパートとして働いていました。子どもには軽度の知的障がいがあります。子どもは大人しい性格で、小さい頃はよく私たちの後ろに隠れるようにしていました。人が多い場所が苦手で話すことも苦手なので、口数は少ないです。
抽象的な表現は理解が難しいため、「○○と○○ではどっちがいい?」といった具合に、具体的に話をするようにしていました。
家では子どもと一緒に洗濯物を畳んだり、私が声をかけながら食事の片づけを手伝ってくれたりしました。また、子どもだけでは自分の書類の整理や管理が難しいため、一緒に書類を分別して、私が管理しています。買い物に行くと、同じ商品でもパッケージが違うと買わないことがあります。「見た目は違っても、中身は同じだよ」と説明しますが、「見た目が違うからダメ」と言い、自分が見たパッケージの商品でないと買おうとはしません。
 特別支援学校(中等部・高等部)では、子どもは仲良しの友達もでき、楽しく通っていたようです。特別支援学校(高等部)を卒業後は、作業所に通い始めましたが馴染めなかったのか、環境が合わなかったのか、次第に休みがちになり、最終的には作業所を辞めることになりました。
特別支援学校(中等部・高等部)では、子どもは仲良しの友達もでき、楽しく通っていたようです。特別支援学校(高等部)を卒業後は、作業所に通い始めましたが馴染めなかったのか、環境が合わなかったのか、次第に休みがちになり、最終的には作業所を辞めることになりました。
相談員さんは心配してくださり、何度も家に来てくれて、新しい作業所を紹介してくれました。その後、子どもは新しい作業所に通い始め、楽しく過ごせているようで、休むことなく通うことができています。
私たち夫婦は、子どもに障がいがあるため、この子を守らなければならないと思いながら暮らしてきました。
しかし、ある日、夫が交通事故に遭い、寝たきりの状態になりました。夫とは話すこともできなくなり、その後、夫は亡くなり、私は一人で子どもを育てていくことになりました。私の頭の中には、「これから、この子を私一人で育てないといけないのか?」、「私はどうしたらいいのか?」という思いが渦巻き、これからの生活を考えると目の前が真っ暗になりました。夫を失ったことで、何もやる気が起きず、ただ日々を過ごすだけの毎日が続きました。その喪失感から、私はうつ病になり、仕事も続けるのが難しくなりました。
ある日、子どもが作業所に行っている間に宅急便が届きました。宛名を見てみると、子ども宛ての荷物でした。いつもは子どもから「○○が欲しい」と聞いて一緒に注文していたので、私が注文したものではなく驚きました。子どもに尋ねると、広告を見て、自分で注文したとのことでした。また、別の日にも子ども宛ての荷物が届きました。
 私は、緊急時のために子どもに携帯電話を持たせています。迷惑メールもたくさん届きますが、子どもはその内容を理解できていないため、知らずにメールをクリックしてしまうことがあります。
私は、緊急時のために子どもに携帯電話を持たせています。迷惑メールもたくさん届きますが、子どもはその内容を理解できていないため、知らずにメールをクリックしてしまうことがあります。
ある日、お金がたくさん貯まるという詐欺メールが届き、子どもはその内容が分からないまま押してしまいました。
その結果、携帯の画面にはお金の支払い催促の文字が何度も表示され、子どもはパニックになりました。画面の内容が良くないことは理解していたものの、具体的な内容までは把握できていませんでした。
その時、子どもはすぐに私に教えてくれましたが、その後も同様の内容のメールが何度も届くようになりました。これにより、子どもは不安になり、体調を崩してしまいました。幸い、大事には至りませんでしたが、今後、何も分からないまま詐欺被害に遭ってしまうのではないかと、私はとても不安になりました。
現在は作業所にも休まず通えていますが、また休んで行かなくなったらどうしようという不安もあります。
私自身も、自分の体調をなんとかしないといけないと思っています。しかし、もし私もいなくなったら、この子はどうなってしまうのだろうと、ますます不安が大きくなっています。
子どもの同級生の親同士でも、私たちがいなくなった後のことについて話したことがあります。その時は、私も元気で何の心配もなく暮らしていたため、大丈夫だと思っていました。
しかし、子どもの携帯のことや宅配便のことなどがあって、これからのことがとても不安になりました。
 子どもの将来について不安に思い、作業所のスタッフの方に話をしたところ、親身に話を聞いてくれました。スタッフの方は、私の体調のことも気にかけてくださり、他の福祉関係者の方にも相談してくれました。現在、私は福祉関係者の方々と一緒に、親亡き後の準備を進めています。
子どもの将来について不安に思い、作業所のスタッフの方に話をしたところ、親身に話を聞いてくれました。スタッフの方は、私の体調のことも気にかけてくださり、他の福祉関係者の方にも相談してくれました。現在、私は福祉関係者の方々と一緒に、親亡き後の準備を進めています。
障がい者等の家族が安心して
親亡き後を託せる社会を実現するために
障がいのある方々は、親亡き後も、これまでの生活を維持するための支援が必要となるほか、悪質な勧誘や詐欺などの被害に遭いやすくなります。そのため、私たちは、「障がい者等の家族が安心して親亡き後を託せる社会の実現」という目標を掲げ、解決に向けた活動やその活動に必要な財源確保に向けた取り組みを行い、活動の実現を目指します。
具体的には、「家族と同等の本人理解(意思決定支援)」「身の回りの手助け」「適正な医療」「契約・手続き」「財産管理」「住まい」「収入」「孤独・孤立防止」「悪徳商法・財産侵害」「移動支援」「災害」の主な11の問題に焦点を当て、本人の自己実現に向けた支援が親亡き後も継続できるよう、課題解決に取り組み、社会的インパクト(成果)につながる活動を行います。
「親亡き後問題」の解決に向けた取り組み
生活に必要な契約・手続きができる活動
法人後見事業、日常生活自立支援事業、点訳・音訳ボランティア等
日常的な金銭管理ができる活動
法人後見業務、日常生活自立支援事業等
財産管理ができる活動
法人後見業務、日常生活自立支援事業等
悪徳商法等の被害防止、サポートができる活動
法人後見業務、日常生活自立支援事業等
災害時等の緊急時に対応することができる活動
要配慮者個別避難計画作成事業等
孤立・孤独防止の活動
集いの場(サロン)事業、互近助パントリー事業等